
看護師2年目になったけど、全然仕事できない・・・
看護師2年目は業務量が多い、プリセプターがいなくなるなど体力的にも精神的にも辛い時期となる場合もあります。

私は1年目より2年目が辛かった。教育をしていても、2年目ナースは悩みが多かったよ。
この記事では、2年目看護師が「仕事ができない」を克服して成長する方法を紹介します。
看護師2年目が仕事ができないと思ってしまう場面
- 1年目と比べられる
- 自分の業務を時間内に終わらせられない
- 自分だけ遅くまで残業している
- 重症患者の観察やアセスメントの抜けを指摘される
- わからないことが多い
看護師2年目は、できない技術や一人で判断できないことが、まだ多くあります。
先輩と同じように1人としてカウントされるけど、自分の能力が追い付いていなくて「できない」と感じやすいです。

さらには先輩と後輩、両方からのプレッシャーもあるよね
看護師2年目が「仕事できない」を克服する方法
達成可能な行動目標を決める
自分で行動を決め、「できた」という体験が、仕事への自信となります。
行動目標は、少し背伸びをしたら達成できる程度の、簡単な目標を設定することがポイント。
高すぎる行動目標は挫けてしまう可能性があり、失敗体験に繋がるため、より「できない」気持ちを大きくしてしまいます。
- ラウンドし終わったら、受け持ち患者全員の経過票を確認する。
- わからないことを1つ、その場で必ず調べ、ノートに書く。
- ルートキープの準備をしてからラウンドへ行く。
小さな行動目標を達成することで、業務の習慣化を図り、最終的には2年目の到達目標につなげていきます。
まずは、簡単な目標を、毎日達成できるようにし、できたことを認めていきましょう。

重要なのは、決して人と比べないこと。
急性期病棟では、一般的に仕事が速い人が評価される傾向があるけど
課題はそれぞれ違うよ!
PDCAサイクルを繰り返す
PDCAと言われるサイクルをまわすことが重要です。
重要なのは、Check(評価)とAction(行動)です。
自分が実施したケア、体験した技術、場面対応などは
「なんでかな」
「どうすると良かったのかな」
「あの先輩はこんな風に対処してたな」
「次はどうやろうか」
という具合に振り返って次の行動に活かしましょう。
失敗しても、振り返って次に活かせれば、必ず成長していきます。
2年生は、失敗こそ価値です!

私は、もっと失敗しておけばよかったなあ、と思ったよ。
結果的に、転職した5年目の時にすごい苦労したよ(涙)
ちなみに、Plan(計画)から始まるPDCAサイクルですが、プランの考えすぎは注意です。
朝の時点で完璧な1日のスケジュール(プラン)を立てるのは不可能ですよね。
イレギュラーは起きるし、会って初めてわかる患者さんの情報もあります。
そのため、Pは適度に、ざっくりと。行動から始めましょう。
計画 → 実行 → 評価 → 行動 → 評価 → 行動 →・・・
イメージとしては少しずつ成果を積み上げつつ、2サイクル目以降は行動→評価を繰り返します。
初めてのことは挑戦してみる
経験を増やすことで、単純にできることが増えます。
病態理解も深まり、異動や転職でも武器になります。
- 初めての処置介助につく
- 他科の緊急入院をとる
- 普段あまりない手術やカテ治療などを受け持つor見学させてもらう
処置や手術、他科の入院、当該科以外の患者の受け持ちなど、初めてのことに挑戦してみましょう。
ただし、通常の業務量が多く、さらに新しいことが追加になると、キャパオーバーになる可能性があります。
自分の受け持ち患者へのケアがおそろかにならないよう、リーダーと相談してみましょう。

新しいことの経験は、ストレスも大きいです。フォローしてくれる先輩やリーダーがいるか、その日のメンバーを見て今日はチャレンジ日!と決めるのも◎
先輩に仕事のやり方を聞く
看護師は質問しないで自分で調べる!という文化がありますよね・・・
ですが、仕事のやり方は経験者に聞くのが一番です。
「薬の副作用がわからない」
この場合は、答えが決まっているので、書籍や薬剤情報などで自分で調べられますよね。
一方で、「8人の受け持ち患者を午前中にラウンドし終える方法がわからない」場合、「●●病院 ●●病棟 1日のスケジュール コツ」と調べても答えは出てきません。
病棟の先輩であれば、「どうやって工夫したか」「まわる順番や患者さん元でやっていること」など具体的な方法がわかるはずです。
自分に合った正解は1つではないので、複数人の意見や方法を取り入れてみると良いでしょう。
患者さんにフォーカスして勉強する
やっぱり、勉強は必要なんですよね。
知識は自分と患者さんを守ります。
ただし、看護師2年目以降は、患者さんを中心とした関連図のような勉強方法がおすすめです。
まずは、自分の受け持ちや気になる患者さんを1人ピックアップしてみましょう。
興味関心があることの方が、頭に残りやすく、大人の勉強方法は関連付けによって記憶に残りやすくなります。
アセスメント力をのばす基礎は、経験と学習を結びつけることだと考えます。

1日や2日で効果が出るものじゃないので、1年かけて焦らずやっていきましょう。
まとめ
看護師2年目は、先輩と後輩のプレッシャーや能力以上の業務量に心が折れそうになる時期。
一方で、仕事への取り組み方で大きく成長する時期でもあります。
課題を見つけ、挑戦と失敗を繰り返し、コツコツ積み上げた日々が、必ず「できない」を克服できるよようになります。
この辛い2年目を乗り切ることで、看護師としてはもちろん、社会人としても大きく成長するナースを毎年見てきました。
辛いけど、得るものも多い1年なので、先輩の力を借りて乗り越えてほしいな。

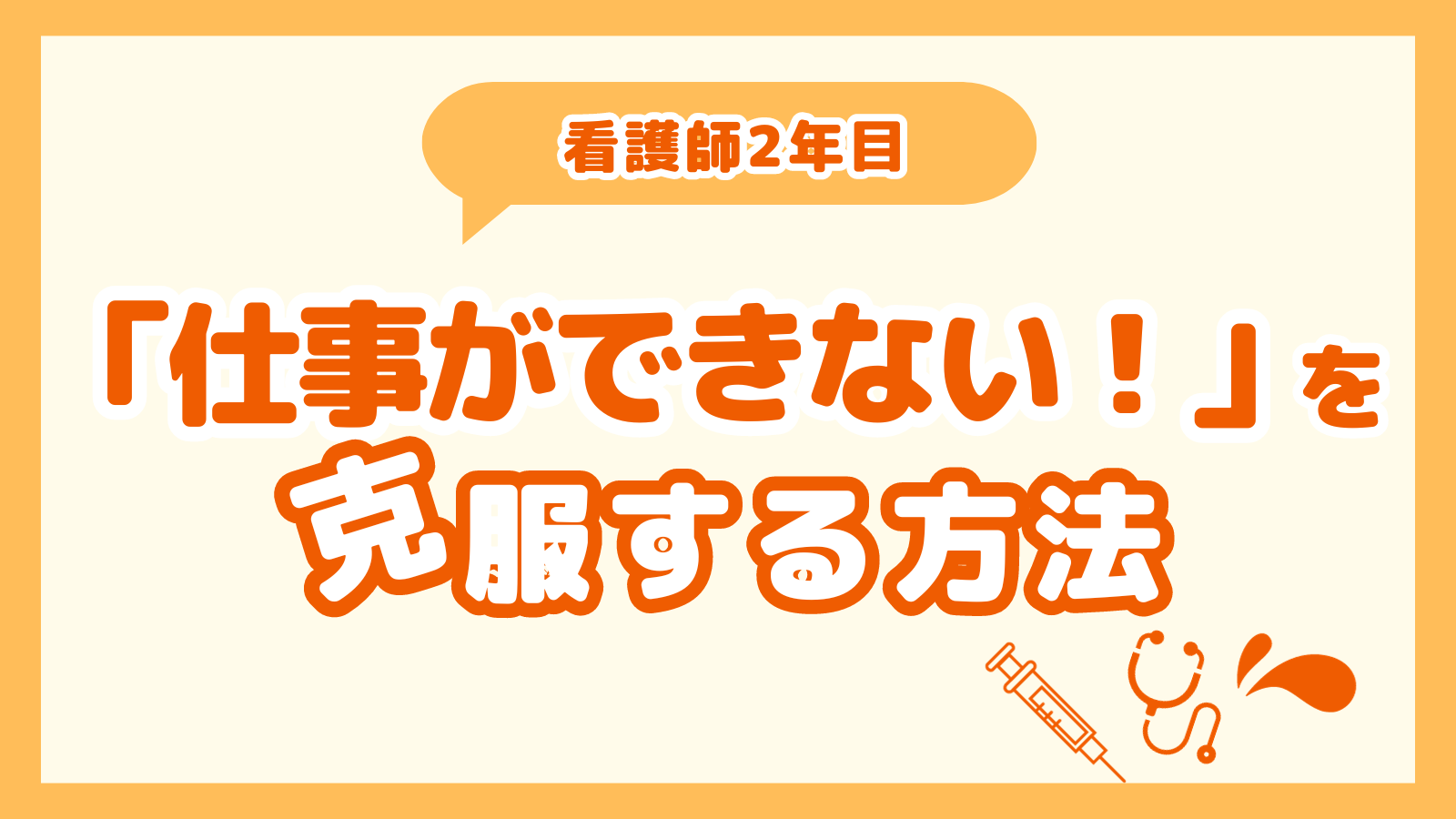
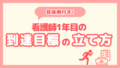
コメント